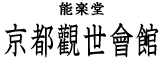第66回 京都観世能
主催:京都観世会
(能) 安 宅 味方 玄
勧進帳
延年之舞
(狂言)二千石 茂山七五三
(能) 大原御幸 片山九郎右衛門
(能) 恋重荷 河村 晴道
S席(1階正面指定席) ¥13,000 予定枚数終了
A席(1階脇正面中正面指定)¥11,000 〃
B席(一般2階自由席) ¥6,500 〃
学生(2階自由席のみ) ¥3,500 〃
※おかげさまで予定枚数を終了致しました。
演目解説
兄頼朝の命により平家を壇ノ浦に滅ぼした源義経は、都を守護していたが、梶原景時の讒奏(ざんそう)や、人心を集めた義経への頼朝の危機感から、都を追われる身となった。義経が若年期を過ごした奥州平泉の藤原氏を頼み、一行は山伏姿に身をやつして北陸道(ほくろくどう)を遁走する。頼朝はこれを捕えるため、各所に新関を設けていた。
安宅の湊(石川県小松市辺り)に着いた一行は、安宅にも新関が立ち、山伏を捕えることを知り、弁慶の計略で義経を剛力(荷負いの人夫)に仕立て、関の突破を謀る。しかし関守は、山伏はすべて討ち取るとして通してはくれない。ならば尋常に討たれようと、最期の勤めを始める。その勤めの言葉の中で、真の山伏を討ち取れば熊野(ゆや)権現(ごんげん)の罰が当たると威すと、関守は怯(ひる)み勤めを制す。そして今度は勧進帳(チャリティの趣意書)を読めと所望する。弁慶は関守に、自分たちは東大寺再興の勧進の山伏だと偽っていたのだ。弁慶は即座に、勧進帳とは無関係の巻物を取り出し、即興で勧進帳を読み上げる。関守は感服し、一行を通す。しかし剛力姿の義経が怪しまれ、留められる。一行は刀に手を掛けるが、弁慶はこれを抑え、この剛力が主君ではないことを証すため、金剛杖で散々に打ち据える。それでも剛力を留めようとする関守に対し、荷負いの剛力に目を懸けるのは盗人であろうと、刀に手を掛け一丸となって迫り来る山伏たち。終に関守は一行を通す。
関を遁れ、一行は休息をとる。弁慶は、主君を打ち据えた非礼を涙ながらに詫びると、義経は、今の機転は天の加護と慰める。そして自らの不運を嘆く。
関守は先刻の非礼を詫びるため、一行に追い着き酒を勧める。弁慶はこれを受け、延年を舞い、急ぎ奥州へ下っていった。
判官(ほうがん)贔屓(びいき)という言葉があるが、九郎判官義経はまさに、武家社会の抬頭とその成果としての鎌倉幕府の樹立のために頼朝に利用され、捨てられた悲劇の英雄と言えよう。日本人には、体制の大義に裏付けられた権力者より、その陰で滅ぼされていった悲運の者たちに憧憬を抱く傾向がある。能作者もまた、大義より人間性を重視する人々の方に視点を置いていることに注目したい。
「勧進帳」は、シテ一人が勧進帳を読む小書(特殊演出)。「延年之舞」は、〈男舞〉の途中で囃子が特殊な演奏に変わり、シテは自ら掛け声を掛けて勇壮に飛び上り、「延年」を真似ぶ。
安徳天皇を初め、平家の一門は壇ノ浦に沈む。帝の母・建礼門院徳子も入水(じゅすい)するが、源氏の武士に引き上げられ、命ながらえて大原の寂光院に籠り、平家一門の菩提を弔っている。
後白河法皇は、建礼門院(女院)を訪うため、大原へ御幸されるとのこと。その御幸の道の清め(整備)をなすよう、臣下が告げる。
寂光院では女院が、同じく尼の姿となった阿波内侍(あわのないし)と大納言局(だいなごんのつぼね)と共に、平家一門の菩提を弔いつつひっそりと暮らしている。都を離れ、俗に交わらず、仏に仕えることだけが心の安らぎである。女院は今日も、仏に供える花を摘みに、大納言局を伴い山へ上る。
法皇の一行は、青葉に遅桜が残る大原へ御幸を進め、寂光院に着く。内侍は萬里小路中納言(までのこうじのちゅうなごん)に、女院の留守を伝え、中納言は法皇にこれを伝える。法皇は女院の帰りを待つ。
山より帰ってきた女院に、内侍が法皇の御幸を伝える。突然の来訪に、女院はあの悲しい現実に引き戻されてゆく。水に月を写せば、そこには我が子安徳帝の面影が映り、遠山にかかる白雲は、花が散るように消えていった平家一門の形見に思える。
そして法皇との再会。法皇は、女院が生きながらに見たという六道の有様を語らせる。女院は戦の地獄のような体験を、苦しみながら語る。法皇は更に、安徳帝の最期を語れと言う。女院は教経の最期、知盛の最期、二位殿と安徳帝の最期、そして自らの入水を語り、法皇との再会の辛さ悲しさに涙を止めることができない。
やがて還幸(かんこう)の時となり、都へ帰る法皇を、女院は涙を堪えて見送る。
世阿弥は『平家物語』に取材し、多くの修羅能を書いた。禅竹は『熊野』『千手』『小督』(*『仏原』『二人静』)など、女性の視点から『平家物語』を取り上げているようにも思える。この『大原御幸』にも、女性的価値観から見えてくる、戦の虚しさと悲しさが描かれているのではないだろうか。
*この二曲は禅竹作の可能性があるもの。
白河院は菊を寵愛されていた。山科荘司(やましなのしょうじ)という老人が、その菊の世話をしていた。あるとき荘司は、女御(帝の妃)の姿を垣間見、恋をしてしまう。それより仕事が手につかない。臣下が荘司を呼び出し、恋をしているのは真かと問い糺す。荘司は、何故ご存知かと肯定する。そこで荘司に課題が与えられる。「恋重荷」と名付けられた美しい荷を持って、庭を百度も千度も廻れば、その間に女御が姿を見せてやろうというのである。荘司は、女御に今一目会いたい一心で荷を持とうとするが、持ち上げることさえできない。恋するゆえに持てぬ重荷と、命を懸けても軽すぎる自分の命。それでも恋のため、何としても持とうとする荘司。遂に力尽きてしまう。それならば恋死(こいじに)し、この怨みを女御に思い知らせようと命を絶つ。 ―中入―
荘司の死が臣下に伝えられ、臣下は荘司を哀れに思う。恋重荷とは、荘司の及ばぬ恋の心を止めるために、持つことのできない岩を美しい錦で包んで軽く見せ、恋が叶わぬゆえに持てないと思って荘司は恋を諦めるであろうという方便だったのだ。臣下は荘司の死を女御に伝え、女御は臣下に促され、荘司の死骸を見、憐みの歌を詠まれる。しかしそれより、身動きができなくなる。やがて悪霊の姿になった荘司が現れ、岩の重荷が持てるものかと怨みを述べ、女御を責め立てる。その後、跡を弔われた悪霊は怨みを翻し、女御の守り神となって、千代(ちよ)の影を守ってやろうと言って帰ってゆく。
古曲『綾(あや)の太鼓(たいこ)』を世阿弥が改作した作品と考えられる。鳴らぬ鼓を老人に打たせる他流の『綾鼓(あやのつづみ)』が、原曲に近い形であろう。世阿弥はモチーフを鼓から恋重荷に変え、より詩的に、また恋そのものの本質を重荷と捉えることに成功している。うら若い女性と老人、帝の妃と庭掃きの人夫。恋などあり得ないと思われたが、老人は命を捨てることで恋を成し遂げている。しかも「千代の影を守らん」とは、永遠に恋し続けるという強烈な意思表示とも受け取れる。恋の普遍性、永遠性を見事に描いた曲と言えよう。
(河村晴道)
出演者紹介
CAST

味方 玄
Mikata Shizuka
日本能楽会会員

茂山七五三
Shigeyama Shime
日本能楽会会員
重要無形文化財保持者
(各個認定/人間国宝)

片山九郎右衛門
Katayama Kuroemon
日本能楽会会員

河村 晴道
Kawamura Harumichi
日本能楽会会員