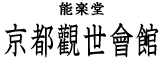第67回 京都観世能
主催:京都観世会
(能) 木 曽 杉浦 豊彦
願書
(狂言)膏薬煉 茂山千五郎
(能) 卒都婆小町 青木 道喜
一度之次第
(能) 海 士 分林 道治
懐中之舞
S席(1階正面指定席) ¥13,000
A席(1階脇正面中正面指定)¥11,000
B席(2階自由席) ¥6,500
学生(2階自由席) ¥3,500
WEB予約・購入はこちら
演目解説
平家一統の世は終わり、東国より源氏が抬頭する。木曽義仲はその先鋒として平家と戦っていた。平家は越前国(現福井県)燧ヶ城(ひうちがじょう)を攻め落とし、十万余騎で加賀(現石川県)越中(現富山県)の境の砺波山まで押し寄せる。義仲方は僅か五万余騎。計略によって勝つべく、味方を七手に分けて、自らは一万余騎で植生(はにう)に陣を取る。
さて、陣より北に当たって山の茂みに、朱塗りの社殿が見える。あれは如何なる神を祀る社かと池田次郎に尋ねると、あれこそ植生の八幡宮で、この陣もその御領の地でありますと答える。義仲は、八幡の御領内に陣を取ったことも吉兆であると喜び、後代の為と、この戦の勝利の為に願書を奉納したく思い、覚明にこれを書かす。覚明は箙(えびら)の中より小硯と料紙を取り出し、即座に願書を書き付け、義仲の御前で朗々と読み上げる。その見事さに一同感銘を受け、さすがに文武の達者と覚明を褒め称える。義仲は上差(うわざし)を覚明に渡すと、覚明はこれを願書に取り添え、八幡に奉納する。
やがてこの地の人々が戦の門出を祝し、酒肴を奉る。義仲は更に喜び、覚明に戦勝を祝う酒宴を促し、舞を所望する。覚明は勇壮に舞う。すると八幡社の方より山鳩が幾羽も飛び来り、味方の旗手に翔る。これこそ神が戦勝を納受し給う証と一同は伏し拝み、いよいよの神の加護を念ずる。
この八幡の神力によって、義仲は平家の大軍を倶利伽羅(くりから)ヶ谷に追い落し、勝利を得たのであった。
八幡は戦神であり、源氏との縁は深い。頼朝が後に幕府を開くが、先ず手掛けたのは鶴ヶ岡八幡宮の造営であり、鎌倉の街も政治機構も、八幡を軸に構築されているように思われる。この曲にも八幡礼賛の主題が響いている。そして前段の山は、覚明が見事に読み上げる願書であり、後段の山は、直垂の長袴を巧みに扱って舞う勇壮な男舞であろう。静と動の構成も見事である。
『安宅』の勧進帳、『正尊』の起請文、『木曽』の願書を「三読物(さんよみもの)」として重く扱う。中でも願書は拍節ともに、殊に難しい。
小野小町といえば、和歌に優れた絶世の美女として知られている。しかし能では、『卒都婆小町』『鸚鵡(おうむ)小町』『関寺(せきでら)小町』のように、百歳にも及ぼうとする老女として描かれる曲が多い。懐旧、有為転変、無常という主題を描くとき、小町はとても大切な存在でもある。
老いた小町は顔を笠に隠し、杖に縋(すが)って憂き身を嘆き、昔を想い、今を恨む。そして歩き疲れて朽木に腰を下ろす。
高野山より都へ上る僧二人が、この老婆を見つける。彼女が腰掛けているのは、なんと卒都婆ではないか。僧は彼女に、それは卒都婆であることを教え、別の所に休むよう教化を始める。ところがこの老婆、僧の教化に応えるどころか、悉く論破してゆく。「本来無一物」と悟りの言葉に至って、僧は「まことに悟れる非人なり」と、老婆を礼拝する。老婆は戯れの和歌を詠み、僧を躱(かわ)す。
僧の問いに答え、小町は名を明かす。そして老残の身を恥じ、路頭で物を乞う様を真似ぶうち、物憑きの風情となる。僧が尋ねると、小町に心を寄せた多くの男たちの中でも、殊に思いの深かった深草少将(ふかくさのしょうしょう)が憑いたと答える。更に少将の形見の立烏帽子(たてえぼし)と狩衣を身に纏い、少将が小町のもとへ百夜通(ももよがよ)いをし、九十九夜目に息絶えた有様を見せる。
物憑きから醒めた小町は花を仏に手向け、悟りの道に入ろうと手を合わす。
『卒都婆小町』は、観阿弥作、世阿弥改作と考えられる。小町と僧の問答(卒都婆問答)では、卒都婆の功徳をめぐって論を深め、教化を始めた僧が小町に教化されてしまうという面白さがある。また百夜通いの再現の場面では、一途な恋を軸にしながらも、憑き物の怪しさと、それ自体を芸能化する大和申楽の本質である「ものまね」の芸質が色濃く残り、古態を留めている。舞の要素が全く無いのが、この曲の大きな特徴でもある。
「一度之次第」の小書により、冒頭の「次第(登場の囃子)」でシテが出、ワキとワキツレはシテが卒都婆に腰掛けた後に登場し、教化を始める。
藤原不比等(ふひと)(淡海公(たんかいこう))の妹は、唐の高宗皇帝(こうそうこうてい)の后に立ち、唐より藤原氏の氏寺である興福寺へ、華原磐(かげんけい)・泗浜石(しひんせき)・面向不背の珠(めんこうふはいのたま)という三つの宝が贈られた。二つの宝は無事に乎城(なら)に着いたが、名珠は讃州(現香川県)志度の沖で龍宮に獲られた(海難に遭い沈んだ)。淡海公はこれを嘆いて支度の浦に下り、一人の海士と契り、子を儲ける。海士はこの子を世継になすとの約束を得、命を賭けて海中に潜り、龍宮より玉を取り返したが、守護神に追われ、自ら乳房の下を切って玉を隠し、命綱を引いて船上に引き上げられる。こうして玉は藤原氏のものとなり、この子は世継として成長する。藤原房前である。『海士』はその後日譚として、房前の志度への下向から始まる。
十三歳になった房前は、母の遺言と自らの出生の秘密を知るため、志度に下る。そこで一人の海士に出会い、名珠を潜き上げたのもこの浦の海士であることや、その海士の子が今の房前の大臣であると聞き、自分こそ房前と名宣る。海士は驚き、房前のまだ見ぬ母への思いを知り、涙を流す。所望により、海士は玉取りの有様を詳しく仕方語りに顕し、やがて房前の母の幽霊であることを明かして波に消える。 ―中入―
所の人より海士のことを詳しく聞いた房前は、母の追善の法要を行う。すると龍女の姿となった母の霊が現れ、弔いへの報謝の舞を舞い、仏法繁昌の霊地となった志度寺を礼讃する。
支度寺の縁起と海士の玉取りを中心にした古曲に、世阿弥が、龍女成仏の思想を基にした舞を取り合わせた作品と思われる。大和申楽の「ものまね」の芸質に、例えば天女の舞のような近江猿楽の「かゝり」と言われる芸質を取り込んでいった過程が見える。具象から抽象、象徴化することに猿楽の未来を見出した世阿弥の才能が知られる作品である。
我が子のためには命も惜しまぬ母性愛が、見事に一曲を支えている。
常の演出では、龍女が舞を舞う前に経巻を房前に渡すが、「懐中之舞」の小書では龍女が経巻を懐中して舞い、舞の最後に房前に渡す。舞の途中に橋掛りに行き、静かに止って思い入れをする「クツロギ」もあり、装束も常と変わることが多い。
(河村晴道)
出演者紹介
CAST

杉浦 豊彦
Sugiura Toyohiko
日本能楽会会員

茂山千五郎
Shigeyama Sengoro
日本能楽会会員

青木 道喜
Aoki Michiyoshi
日本能楽会会員

分林 道治
Wakebayashi Michiharu
日本能楽会会員